僕とミゲルのチリ・ワイン紀行3000km!-2-
チリワインに起こった「地殻変動」の現場を取材するべく、2007年の師走、僕は初夏の南米チリでワイン産地をめぐる旅をしていた。旅の相棒はスペイン語しか話すことのないドライバーのミゲル。さて、二人の珍道中の顛末は?
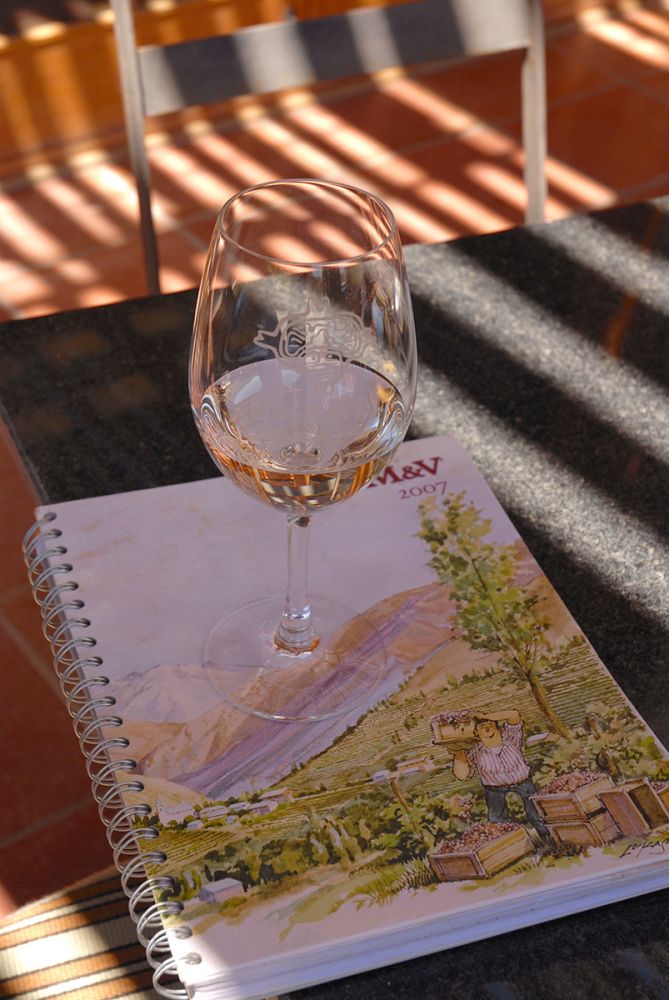
そのワインを口にしたとき森の中にいると錯覚した
4日目。われわれは南下を続けカチャポアル・ヴァレーに入った。アナケナというワイナリーがあるアルト・カチャポアルの辺りはアンデスのすそ野と海岸線の間にも2000m級の山地があり、谷間というよりも盆地と呼ぶべき地形。冷たい海風が遮られる分、他のヴァレーよりも暑くて乾燥している。
「その気候的特徴がカルメネールの栽培に求められる条件そのものなのです」とテイスティング・グラス片手に力説するのは、醸造家のゴンサロ・ペレスだ。われわれの間に据えられたテーブルには赤白合わせて14本のボトルが並んでいる。単一畑もののカルメネール2006はそのなかの9本目だ。ワインのプロたる者なら試飲で酔っぱらったりはしない。香りを嗅ぎ、味を確かめたら口の中のワインは呑み込まずに捨ててしまうからだ。しかし僕は味というものは喉を通ったときの感覚も含めて味だと信じているので、ついついゴクリと呑み込んでしまう。つまりは昼間っから酔っぱらうことになる。ただ、ありがたいことに、良いワインというものは酔っぱらった状態で飲んでも、何杯目に飲んでもやはり旨いのだ。そのスパイシーで複雑味のあるカルメネールを口にしたとき僕は一瞬森の中にいるような気がした。この旅の最初から興味津々だったカルメネールだが、じつは何種類か飲むうち、その青臭さに閉口し始めていた。ちょっと驚いたような僕の表情に気づいたゴンサロが得意げに言う。「適地適品種ですよ。あとは房の上の葉を落として日に当ててやり、収穫をぎりぎりまで遅くしてやればカルメネールは本来の力を示すのです」



無給なのに一番よく働くスタッフとは?
カーブやアップダウンというものがほとんどない、ひたすら真っ直ぐな道をミゲルの運転する車はひた走った。われわれのコミュニケーションはここにきて格段の進歩を見せ、この日は朝から僕が彼に日本語を教えている。といっても、車窓から見える動物──犬、猫、牛、馬、鶏など──を表す日本語を教えているだけだが。いい歳をした大人が2人で反復練習をする声が車中に響く。「ウマ」「ウマ」「イヌ」「イヌ」……。
われわれはコルチャグア・ヴァレーに入った。いま最も勢いのあるワイナリーが畑を接して覇を競う地区。まずはラベルに描かれた自転車がトレードマークのコノ・スルへ。93年創業の若い会社だが、エコとオーガニックを前面に押し出した戦略が当たって急成長。いまでは輸出量第3位(2008年当時)の一大ブランドだ。
「ラベルの自転車は、毎日自転車をこいでワイナリーに通ってくるスタッフたちへのオマージュなんだよ」と醸造家のマティアス・リアス。不得手な英語に詰まりながらも、相手に何かを伝えようとする熱意が伝わってくる。こういう人が造るワインは信用できる。畑を見て回るのに車がいいか自転車がいいかと訊かれ、僕は「もちろん自転車で!」と即答したが、サドルに跨ってすぐ後悔することになった。デコボコで軟らかい土の上を、重いカメラバッグを背負って自転車で行くのは正気の沙汰ではない。バランスが取れない、地面の凸凹にハンドルを取られる、マティアスに置いてきぼりにされないようにするだけで精一杯だ。それでも澄み切った晴天の下、自転車の上からぶどう畑を眺めるのは心躍る体験だった。
「樹間に草花を植えているのは、ある種の害虫がぶどうよりも花の香りに惹かれる性質があるから。幹に巻かれた包帯のような白い紙が見えるかい? あれは地中から幹を伝って這い上がるブリートという害虫を追い払うためのもので、ニンニクオイルがしみ込ませてあるんだ」とマティアスが解説する。他にも、赤蜘蛛という害虫には天敵の白蜘蛛を放すことで対抗するなど、オーガニックのための工夫がいくつも施されている。畑での日々の仕事はさぞやたいへんだろう。ガチョウが金網で囲われた一角で自転車隊は停車した。
「わが社で最も役に立つ社員たちだよ。しかも給料はタダだ」
800羽いるというガチョウは畑に出て害虫をついばむだけでなく、お尻から有機肥料を振りまいてくれるというわけだ。


「愚か者」というワイン名に込められた造り手の確信
コルチャグア・ヴァレーで唯一の町らしい町、サンタクルスを出てティンギリリカという舌を噛みそうな名前の川を渡ると、アパルタ地区に出る。90年代後半以降、プレミアム・ワインをいくつも世に送り出し、いまやその土地を手に入れるにはボルドーの銘醸地と同額かそれ以上のお金が必要だという。モテンスで僕を待っていてくれたのは創業者の一人、ダグラス・ムライだった。
「アパルタに斜面畑を開発したのはうちが最初だよ」よく太った体躯の上に人懐っこい笑顔をひょいと載っけただけ。そんな印象のダグラスが言う。そこはしっかり足を踏ん張っていないと滑っていきそうな急斜面だ。
「98年に傾斜が45度もある岩だらけの斜面にシラーを植えたときには、人にあいつらは頭がイカレたんじゃないかって言われたよ。でもね、私たちには確信があったんだ。傾斜も岩の多いことも含めて、ここの自然条件にはフランスのコート・デュ・ローヌに通じるものがあるとね。ご存じの通り、シラーはローヌの赤の主要品種だよ」
そうして実ったシラーで造ったワインが2000年に初お目見えする。フォリー(英語で「愚か」という意味)は、彼らのパイオニア精神を嗤った者たちへの痛烈な勝利宣言だ。



モンテスでの試飲にはたまたまこのワイナリーを訪れていたアメリカ人女性ワインジャーナリストが同席した。ダグラスに輪を掛けたような太っちょ。真っ赤なワンピースがはち切れそうだ。歳は僕と僕の母親の間くらいだろうか。彼女のコメントがアメリカのワイン市場に相当な影響力を持つことは受け入れ側の尋常ならざる応対ぶりから察しが付いた。単一畑の白・赤、先ほどのフォリーを含む3つのアイコン・ワインと試飲を重ねるうちに、彼女のコメントを通して、アメリカ人がチリワインに求めるものが見えてくるような気がした。彼女のモットーは「オーキー、フルーツ、タニック&イージー・トゥ・ドリンク」。すなわち、樽香がして、果実味があり、タンニンもしっかりと感じられて飲みやすいのがいい、ということ。ワインはそんな単純なものじゃないのになあ、と思いながら彼女の話を聞いていたのだが、例によって酔いもまわり、いつの間にか僕も持論──チリワインの大いなる可能性についての一考察──を展開していた。気が付くと、アメリカ人が口をポカンと開けてこちらを見ていた。やってしまったかな? 別れの握手を交わすときダグラスに「日本はわれわれにとってとても大切なマーケットだ。あなたの意見はとても参考になったよ」と言われた。やっと溜飲が下がった気がした。




最後の目的地リマリ・ヴァレーへはサンティアゴから飛行機で飛ぶことになっていた。アパルタから首都へと戻るドライブはドライバー、ミゲルとの別れの道だった。「不幸な出逢い」から始まったわれわれの関係は時間と共に改善され、いまでは親愛の情を感じるほどになっていた。実直で家族思いで道行く美女に素直に反応するミゲル。バリトンの渋い声で「ウマ」「ウシ」「イヌ」「ネコ」と口ずさむことができる。サンティアゴのホテルの前で車から降り、僕たちはガッチリと握手し、抱き合った。アストラ・ヴィスタ! この次はワインを酌み交わそうな。
ショッカーのアジトのような熟成庫で宇宙人に出会う
4、5年前までチリのワイン・マップにはアコンカグア・ヴァレーより北の産地名は載っていなかった。サンティアゴの北方約400㎞のリマリ・ヴァレーは、それほど新しいリージョンだ。空港のあるラ・セレナまでサンティアゴから空路1時間。南半球では北へ行くほど暖かくなるのだと思いきや、寒流の海に近く、背後にはアタカマ砂漠が控える影響で、日差しは強いが気温はさほど上がらないという。こぢんまりとした空港の出口でちょっとファンキーな女性がガムを噛みながら待っていた。彼女の運転するコンパクト・カーは僕を乗せ、時速140㎞で疾走した。右手に白波の立つ冷たそうな海、左手には灌木やサボテンがあるだけの荒野が続く、生きた心地のしない風景。空気の乾燥はサンティアゴ周辺よりもさらにひどそうだ。「年間降水量は100㎜以下、晴天の日が年300日あるのよ」とファンキー嬢が言う。おいおい、100mmと言えば、日本じゃ、集中豪雨の季節なら半日で降る雨の量だぜ。1時間ほどでワイナリーに着いた。名刺をくれて、初めてファンキー嬢がビーニャ・タバリのPR兼売店担当のマリア=パス・マルティンだとわかった。施設内を案内しながらマリア=パスはこの土地について話してくれた。この辺りは古来スピリチュアル的に磁場の強い場所として知られ、すぐ近くにはヴァリェ・デ・エンカント(魔法の谷)という地名も残る。ショッカーのアジトのようなワイン熟成庫の壁に、ここのワインのラベルにも描かれたお面のような図案が掲げられている。「この線画も近くの洞窟で見つかったものの写しよ。私には宇宙人に見えるわ」とマリア=パス。海まで続く渓谷を望むガラス張りの試飲室でテイスティングをした。白赤5本、すべてに相通じる清潔感と繊細な味わい。それはこの土地の極度の乾燥や昼夜の温度差がもたらすものなのか、はたまた例のスピリチュアル・パワーがもたらすものなのか?
試飲室から出ると、猛烈な風が上着をはためかせた。おなじみの午後の海風が谷を上ってきたのだろう。それがチリ・ワインにデリカシーを与える風であることを僕はすでに学んでいた。



※『僕とミゲルのチリワイン紀行3000km!』は雑誌Hanako(マガジンハウス発行)No.923に掲載された記事・写真に加筆・再編集をしたものです。記事や写真の無断転載はご遠慮ください。(筆者)
Photographs by Yasuyuki Ukita
